フォントの本当
パソコンが普及して、フォントという言葉が市民権を得てきた。関連する世界で仕事をしてきた者にとっては嬉しい限りである。
ただ、コンピュータで扱うすべての文字のことを、フォントという人さえいる。タイプフェイスデザインや、表示されたり印刷された文字までも。ロゴタイプもフォントという人がいるそうだ。正確な意味を理解している人は少ない。
もともとは、欧文活字の用語である。同一書体、同一サイズの活字一式のことだ。印刷会社が活字を導入する時の、基本となるものだ。各文字の使用頻度から割り出して本数を決めるのである。
活版印刷の見学会で、同じ活字が何本も置かれているのを見て不思議がっている人の話を聞いたことがある。写植時代以降しか知らない人にはどうも理解できないことらしい。最近の子供が電話のダイヤルを回せないのと同じで、時代の流れなのである。

活字ケース(写真提供:熊本日日新聞社)
この活版用語だったフォントを、1968年にアルファニューメリック社(現オートロジック社)で、『タイプフェイスを具体的な記録や表示、出力時に忠実に再現し、利用できるようにしたハードウェアやソフトウェア』という意味に転用して使ってからは、こちらの意味で使うのが主流になっている。
タイプフェイスデザインでは、制作する字種の単位として重要な意味を持っている。特に漢字は、『大漢和辞典』で5万字に及ぶ膨大な文字体系なのである。この5万字を1フォントというと、とてもつらい。
辞書を作る場合などを除いては、日常で使われる文字は限られている。通常、2,200字あれば99.8%は表現できるといわれている。しかし、残りのわずか0.2%のために膨大な漢字を用意しなければならないのである。ほとんど使われない文字のために、よく使われる文字以上の労力を費やさねばならないのだ。
日本語のフォント(制作字種)
すべての書体に、使用頻度のほとんどない文字まで用意するのは無駄である。そういう意味でも、1フォントの基準を決める必要がある。活字においても、工程近代化で文字入力キーボードが導入され、字種の規格ができていたそうだ。
文字盤にタイプフェイスを収容する手動写植の場合、文字盤=フォントということになる。従って、収容する字種の選定が重要になる。当初、活字ケースの調査や、漢字に関する研究をもとに、最終的には日下部重太郎『実用漢字の根本的研究』の所説に従い、5,460字と決められた。
それを、使用頻度によって、頻度の高い文字から一級(273字)、二級(2,184字)三級(3,003字)とし、小型文字盤に分割して収容した。なお配列は、活字ケースの部首別配列、タイプライターの音訓配列に対し、採字力のあがる『一寸ノ幅式配列』を採用した。
その後、メインプレート方式の文字盤を採用した時に大きな変更を行っている。新聞社、印刷会社、また国立国語研究所の資料などをもとに、メインプレートに収容する2,862字を選んだ。この文字のうち、頻度の高い文字である一級(600字)を中央に、二級(2,262字)を周りに配置した。
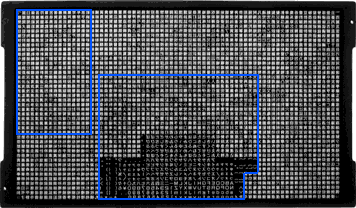
文字盤:メインプレート(提供:写研) □内をクリックすると、別ウインドウに拡大図が表示されます
これに三級字種と記号類を含めたものが、一般的なタイプフェイスの標準的な制作字種であった(これに旧字体の字種と汎用的な字種が追加されることもあった)。メインプレートだけの書体もありえたし、記号類はそのタイプフェイスの特長や目的に合わせたものを収容することが可能であった。
電算写植になってデジタル化され、直接目で確認することができなくなったが、内部の文字コードは基本的には手動写植の配列を踏襲している。これには、文字盤でいう三級文字と旧字体文字、汎用的な文字の一部が標準的に収容されるようになったので、手動機のメインプレートだけの書体は現在のところ葬られている。「オクギ」や「ラボゴ」は、このまま消えてしまうのだろうか。
フォント(収容字種)の設定にあたっては、文字行政との関連も考慮に入れられている。
国語表記について明治以来さまざまな議論や検討が繰り返されてきたが、戦後、当用漢字表(1,850字)等の一連の施策が内閣告示・内閣訓令により実施された。これらの施策は相応の効果をあげてきたが、日常使用する漢字の範囲を制限するという方針は国語の表現を束縛するなどの意見や批判もあった。
このため、文部大臣の諮問を受けた国語審議会では当用漢字表等に変わる一層適切な漢字表として『常用漢字表(1,945字)』を作成した。この常用漢字表は、漢字使用の目安となることを目指しており、制限する性格のものではない。このうち教育漢字(1,006字)が、小学校学習指導要領の学年別配当表に示されている。
これとは別に、人名に用いる漢字については、戸籍法等の民事行政との結び付きが強いものであるとして、法務省の管轄となっている。戸籍法及び同施行規則により『人名用漢字別表(284字)』が選定されている。
一方、通産省関連の日本工業規格(JIS)では、『7ビット及び8ビットの2バイト情報交換用符号化漢字集合』(X0208:1997)が制定されている。関係各機関・企業の協力と膨大な資料の検討を行って制定された1978年(第一次規格)以来、1983年(第二次規格)、1990年(第三次規格)の改訂を経ての、第四次規格である。この改正においても同様な労力と時間を要している。
この規格では、6,879文字(漢字は6,355字)が収容されている。このうち、第一水準漢字(2,965字)は代表音訓の50音順、第二水準漢字(3,390字)は部首画数順である。さらに、新JIS(第三水準、第四水準)への漢字追加策定案が進められている。
この規格は、多くの情報機器に実装されている。日本語フォントの標準になったといえるのではないか。
技術革新は、結果的にセットされる文字の数を多くしてしまい、タイプフェイスデザインの多様化に障害となっているような気持ちさえしてしまう。フォントとして画一化されたことで、書体によっては全く使わないような文字までも制作し揃えなければならないことになってしまう。
頻度の多い字種を限定したフォント(文字セット)が、あっていいのではないか。一般の書体では第一水準だけで十分なのではないだろうか。めったに使わない字種まで、揃えておくことはないではないか。
本来のフォント[文字セット]は、収容する媒体によって制限されているのかもしれない。とすると、新しい意味[記憶媒体に記憶したもの]として使われるようになったのも理解できよう。
字体の事態
制作字種と共に大きな問題になっているのが、字体の問題である。字体というのは、なかなか説明しにくい用語である。
字体とは、概念である。字義を文字として認識できるような点画の組み合わせでまとめた形のことである。実際に表現されたものを骨組みといい、これを字体ということが多い。ここでいう骨組みは、点画上の中心線のことではない。「恵」と「惠」は字義は同じだが、字体は異なるのである。
基準として、『常用漢字表』『人名用漢字別表』がある。この表で定めた字体を新字体と呼び、これ以前の字体を旧字体と呼んでいる。つまり、「恵」は新字体、「惠」は旧字体となる。
この『常用漢字表』には、[字体についての解説]が付けられている。一つは、明朝体活字のデザインの違いに属することであって、字体の違いでないと考えられるものである。字体の上からは、全く問題にする必要はないとしている。
わざわざ解説があるにもかかわらず、デザイン上の差異を字体ととらえている人が、教育関係者に多い。木をはねたら×になったというような話をよく聞く。それで試験に落ちれば人生を左右されることになるのだから、恐ろしいことである。
見出し用のタイプフェイスデザインにおいては、字体の違いだと考えられる範囲でより大胆に処理するケースがある。あまり、画一化されると創作の幅を狭くするのだが。
もう一つは、明朝体活字と筆写の楷書との関係についてである。『常用漢字表』では、字体として同じであっても、明朝体活字と筆写の楷書の形の間には色々な点で違いがあるが、印刷上と手書き上のそれぞれの習慣の相違に基づく表現の差と見るべきだとしている。
さかのぼると、『説文解字』(漢字学の書籍としては最も古い基本的な古典)や、『康煕字典』(康煕帝の勅命により編纂された中国の字書の集大成)に行き着く。
『説文解字』の篆字(てんじ)を楷書に改めた文字を[本字]、古文、籀文(ちゅうぶん)、大篆(だいてん)を楷書に改めた文字を古字という。また、『康煕字典』が正しいとしている字体を正字、世間で通用している正解でない字体を俗字という。俗字の一種で、点画の一部を略して簡略にしたものを略字という。これらをひっくるめて異体字だ。(ああ、ややこしい。ここまで来ると、文字学の世界だ)
『説文解字』から『康煕字典』への流れは、いわゆる字典体(康煕字典体)といって、日本の漢和辞典に引き継がれている。『常用漢字表』も、明朝体活字を用いて例示しているから、この流れだ。これに対し、隷書から楷書への流れを書写体という。「惠」は字典体(=正字)、「恵」は書写体(=俗字)である。(参照)
つまり、書写体では「恵」なのであり、「惠」という書き方はしなかったのである。ところが、フォントとなるとこの両方が要求される(惠は、第二水準だが)。この文字ぐらいはなんとかなるとしても、楷書や行書では描きようのない字体も出現する。
手動写植の文字盤では、楷書や行書の書体では制作されない文字があった。印字される文字が見えたので問題なかったが、デジタルフォントとなると、見えないだけにないと困るのだろう。特に、簡単に書体を入れ替えることができる(明朝体→楷書体というように)だけに、やっかいである。
かなの字種と字体
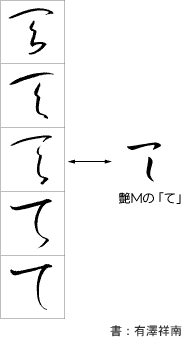
漢字の字種や字体が語られることはあっても、かなについてはあまりなかった。漢字ほどではないにしても、字体の問題は存在しているのである。
私事だが、あるコンテストの出品作で「を」を途中で切ったことがある。これも、ある人から間違いだと言われた。もともと「遠」からきた文字なので、構わないと思ったのだが。
「艶」というかな書体で、「て」という字の字体が間違いではないかと問題になったことがある。途中で筆を上げて2画にして書いていたからだ。こちらは、厳密に言えば変体かなである。他の文字とイメージを合わせるために、同じ漢字「天」からできていて違和感もないことから、あえて採用したらしい。
1900年(明治33年)、帝国教育会国語改良部の「同音ノ仮名ニ数種アルヲ各一様ニ限ルコト(即チ変体仮名ヲ廃スルコト)」という議決を受けた文部省は、8月21日、小学校令施行規則第十六条(第一号表)により、平かなと片かなの字種・字体を一定した。
それまで、今日の字体とは違った文字(変体かな)が数多く含まれ、完成された組織を持ったものではなかった。かなが生まれて1200年、今世紀になってはじめて今日のかなが定着したのだ。

幼児用かななるものがある。多くの教科書会社では、「き」や「さ」の脈絡は小学校低学年では好ましくないから離せというのだそうだ。こういうのが、他の文字にも及び、教科書体だけでなく現代的な書体にまで統一させようとする。デザインの違いを、字体と解釈しているようだ。 仕方なく別バージョンでデザインするのだが、まるで別の書体のようになるのだ。しかも、教科書会社ごとに特徴を出そうとするから色々なパターンができてしまうそうだ。これが拡大されると、書体の存在価値を無くしかねないことだ。
一方で、女子高生によって『マル文字』とか『ヘタウマ文字』といった、一般の人が困惑するような字体のかなが流行したことがあった。かなの字体についても検討する必要がありそうである。
字種と字体の今後
制作字種と字体の問題は、タイプフェイスデザインの上で大きなウエイトを占める問題である。これらは文字行政に関わる事柄であり、決定に従わなければならない。今後とも、検討が繰り返されなければならないし、そうなるであろう。その際、文部省、法務省、通産省と分かれている文字行政の一本化が待たれるのである。
その範囲内では、もっと自由度があってよいと思う。常用漢字以外で使いたい文字があるのはわかるが、すべての書体で必要なのかどうか。字種を多くして書体開発を長期化させるより、多くの書体の登場の機会を与えて欲しいと思う。
また、デザインの範疇の処理を字体と解釈して、画一的に統一することが必要なのかどうか。デザインの幅を狭くしないで、色々な表現ができるようになることが望ましい。教育関係者に訴えたいところである。
参考文献
- 日本工業規格(JIS X0208:1997)
日本規格協会 - 文字に生きる
写研 - フォント関連用語集
日本規格協会 - たて組ヨコ組「東西活字講座」
小塚昌彦/モリサワ - 解説字体辞典
江守賢治/三省堂 - JIS漢字字典
芝野耕司/日本規格協会




