
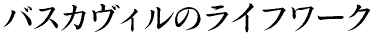
既成のソフトを入手するだけで、好きなオリジナルフォントを作成したり、文字の大きさを自由に変えたりもできる、高度に進化した現代の世の中。それにひきかえ、コンピュータの助けなどなかった遠い昔に活躍した先達にとって、書体をデザインして活字にし、それを印刷するということは、当然ながらとんでもない難事業であったことが想像できます。
書体デザイナーとして歴史に名を残すジョン・バスカヴィル(John Baskerville)は、1706年にイギリスのウスタシャーで生まれました。若きジョンは、バーミンガムで聖職者の屋敷の使用人をしていましたが、彼の能書家としての才能をたまたま発見した主人が、教区の子供達の教材を彼に清書させるようになりました。これがジョンの書体デザイナーとしての第一歩です。やがてジョンはその才能を活かして、学校の「かきかた」教師で生計を立てるようになり、さらに墓石の碑文をデザインして彫る仕事も手掛けたりしました。
こうして一気に書体デザイナーの道をのぼりつめ…と行くのが自然に思えますが、彼はそう単純でも地道でもなかったようです。一説では、より儲けるために高級漆器業という、それまでの経歴とは何の関連もない事業に手を出し、運よく成功を収めるのでした。そしてちょっとした資産家の身分となったジョンは、郊外に家を建てていつまでも幸せに暮らしましたとさ…
と、わけのわからぬままお話が終わってしまいそうになりましたが、ここからが本題です。裕福な中年紳士となったジョンはある日、ウィリアム・キャスロン(William Caslon)による活字見本表に出会います。キャスロンとは、1720年にイギリスに活字鋳造所を造り、現代も「オールドロマン」として親しまれている書体「キャスロン体」を生みだした人物です。
この見本表との出会いが起爆剤となり、ジョンは、その腕を人々に認められ活躍していた過去の日々への熱い思いをつのらせました。情熱断ち難く、彼が書体デザインおよび印刷出版の事業にとうとう乗り出したのは、ジョン・バスカヴィル、働き盛りの44歳を迎えた1750年のことでした。
彼の経営姿勢は利益を全く度外視したもので、最高に美しく良質な書体を開発して優れた印刷物を制作することを最優先にしました。そんなわけで、最初の本の出版になんと七年もの歳月を費すことになり、1757年にやっとの思いで『ウェルギリウス(Virgil)』を世に出すことがかないました。この本の美しさは各方面で大変な称賛を浴び、アメリカのベンジャミン・フランクリンなどは6部も予約したといいます。しかしながら、好評には悪評がついて回るのが世の常、ジョンの本も例外ではなく、“バスカヴィルの活字は目を痛める”という思わぬ批評を受けたりもします。
「バスカヴィルの活字が目を痛めるという評判をよんだのは、細いストロークのせいである。バスカヴィルの活字は、太いストロークと細いストロークの対象が際立っている。彼以前の書家は、先の太いペンで文字を書き、それで活字を作ったが、バスカヴィルは、先の尖ったしなやかなペンで書いた。これが、バスカヴィルの活字を過度に繊細にし、多くの人々を魅了するとともに、他方、目を疲れさすという苦情を集めた理由である」(大輪盛登『グーテンベルクの髭』)
さて、活字用の字体を手書きで作ると一口に言っても、アルファベットの大文字と小文字を一通り書けば、はい、おしまいというものではありません。それはそれはとてつもない労苦と忍耐を強いられる崇高な作業でした。まず、本一冊の中身が全て同じ大きさの文字というわけにいきませんから、大きさのバリエーションが必要です。拡大・縮小なんぞコマンド一発でできてしまう現代と違い、当時は全て自分の手でコツコツ書きあげていました。また、どんなに大きさを変えても、同じ書体であるからにはデザイン上の統一感は不可欠です。
なかなか好評だった『ウェルギリウス』に続いて、グーテンベルク以来の印刷業者の伝統というのか、ジョンもまた聖書を印刷しました。この聖書は彼自身もはりきって取り組んだ自信作で、今日でもバスカヴィル最高の仕事と称賛されているほどの出来だったにもかかわらず、1,250部刷ったうちの半分ほどが売れたに過ぎませんでした。結果、500部あまりを二束三文で本屋に引き渡す羽目になり、これに失望してヤケにでもなったのか、ジョンは印刷所を売りに出したりもしました。もっとも三年後には印刷業を再開しているのですがね。
利益のためではなく、文字や印刷物を愛する者としての欲求と才能のおもむくままに、書体を作り本を出版する人生をまっとうしたジョンは、1795年にこの世を去りました。彼が精根を込めて作った書体は、優れたスタンダードアイテムとして一般に普及し、親しまれながら現代も生き続けています。
現在の私たちは、モニタの前に座り込んで、表示に合わせてマウスをドラッグしたりキーを押したりするだけで、字体の作成や変形などの操作からプリントされたときの出来上がりイメージを知ることまでが、思いのままのあっという間です。しかし当時は、字の大きさを変えた時に見た目がどのように変わるかを確認したくても、活字にして印刷してみるまでは、自分の頭の中でシミュレートするしか方法はなかったのですから、統一感を保つためにどれだけの試行錯誤があったことか、その苦労がしのばれると共にジョンの才能と努力に頭が下がります。
さらに、彼はこるタイプの人で、小さいサイズの字体は細部を省略するなどのデザイン上の工夫をおこたりませんでした。お手持ちのコンピュータで、画数が多めの文字をポイントサイズを変えて表示してみて下さい。
小さいポイントサイズほど省略が見られるでしょう。これは、小さいサイズでは画面で表示しきれないというドット表示ならではの問題が関係しているのでしょうが、バスカヴィルの書体の場合はもちろん違います。
「小さいサイズで細部がいくらか失われたのは技術不足のためではなく、単純な事実として、人間の目はどんな細部も見逃さないので、細かすぎる部分が視覚的なノイズを引き起こし、文章が読みにくくなるということだ。大きい書体ほど、言葉の純粋な意味より、文字自身に注意がそれて、うまく読めなくなる。しかし小さいサイズだと見過ごせることなのだ」(Manfred Klein, Yvonne Schwemer - Scheddim, Erik Spiekermann、田辺晴美訳/Type & Typograhers 欧文書体入門)
活字製作者としてだけでなく出版者としても優秀なジョンは、製本に関しても大いにこり、印刷物に高度の仕上がり感を出すため、わざわざ艶のある紙を作らせたりしました。余談ですがこの紙に対しても、「まぶしくて目に悪い」などという、やっかみ半分の苦情をよこす者がいたといいますから、世の中というのはいろいろです。
また彼は、刊行した本の多くを未製本のまま販売し、購読者の好みにあわせて製本するという、今の出版業界では信じられないような企画も実践していました(逆に中世の頃までは未製本があたりまえでした。)そのため彼の本は値が張り、購入するのはある程度の資産を持つ本のコレクターのような人達が中心だったようです。
執筆:杉山朋子、村松佳子、蛭田龍郎
参考資料
- THE BOOK;The Story of Printing & Bookmaking
Douglas C. McMurtie/Oxford University Press/1943 - グーテンベルクの髭
大輪盛登/筑摩書房/1988 - 印刷文化史
庄司浅水/印刷学会出版部/1957 - Type & Typograhers 欧文書体入門
Manfred Klein / Yvonne Schwemer - Scheddim / Erik Spiekermann
田辺晴美訳/朗文堂/1992 - The MACINTOSH FONT BOOK 2nd Edition
Erfert Fenton/Architecture Design and Technology Press/1989




